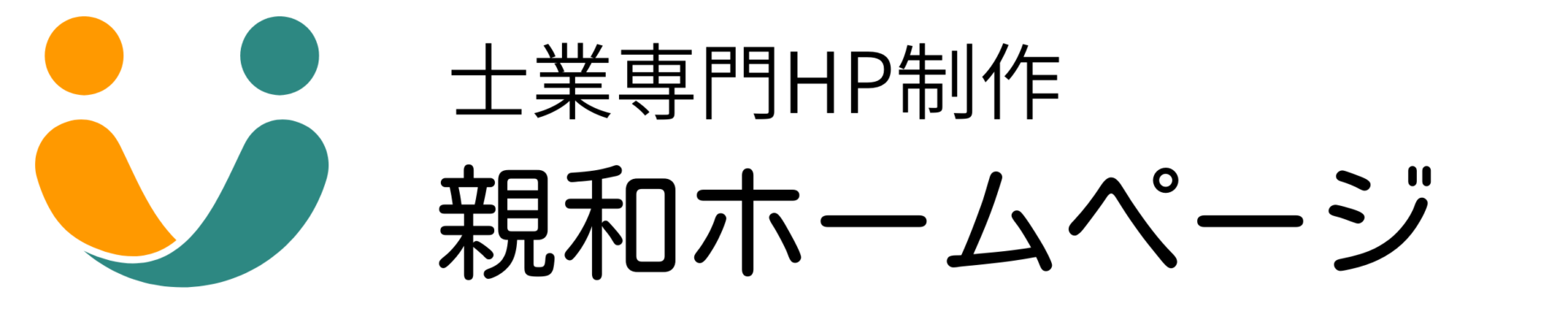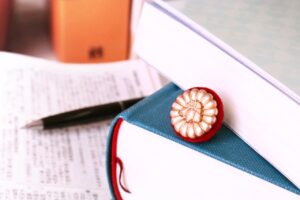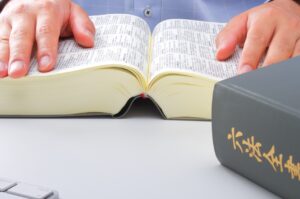こんにちは。士業専門ホームページ制作を手がける「親和ホームページ」代表の前原です。
開業を予定している士業の先生にとって、ホームページは“事務所の看板”のようなもの。
「せっかく作るなら、見た目もキレイで、集客もできるサイトにしたい」——そう思われるのは自然なことです。
ですが、実際には、見た目が良い=集客できるホームページとは限りません。
100万円かけて見た目のいいホームページを制作会社に頼んで作ってもらったのに、集客向きではなくて失敗して作り直した。
こんな士業ホームページの失敗例を聞いたりします。なぜ起こるのでしょうか?
今回はこのカラクリを、ウェブメディア運営歴10年以上のプロが説明したいと思います。ホームページ制作会社からなかなか説明されない検索の仕組みを紹介するので、参考になれば幸いです。
デザインはRPGの能力値でいう「かっこよさ」に値する
ホームページの第一印象を決めるのは、もちろんデザインです。
ウェブデザイナーさんに頼むのは、視覚で先生の印象を誘導するためにあります。
清潔感や信頼感、安心感をビジュアルで伝えるという意味では、デザインはとても大事な要素です。
自撮り写真とチグハグカラーのホームページより、プロのカメラマンが撮って取扱業務に合った色のホームページのほうが、お客さんも頼みたくなるもの。
ただ、士業のホームページを作る時に注意したほうがいいのは、どこまでデザインにお金をかけるかという問題です。
RPGゲームと一緒で、デザイン(かっこよさ)というパラメーターに能力や装備を全振りするのは良くありません。
ネット集客(力)、保守点検費(身の守り)、ブランディング(賢さ)など、ホームページ制作で振り分けるべきパラメーターは他にもあります。
デザインのいいホームページを100万円以上かけて作ってもらったのに、集客ができなくて作り直した。
この失敗例は、デザイン(かっこよさ)に全振りをしてしまい、ネット集客(力)などに力を注がなかったために起こった悲劇です。
では、ネット集客などに力を注ぎたかったら、ホームページのどの部分に力を注げばいいのでしょうか?
ズバリ答えを言うと、文章です。
検索対策( SEO対策)のできるライターにホームページの文章を頼んだほうが、後々の集客力は上がります。
ネット集客のカギを握っているのは“ライター”
検索でホームページを見つけてもらうには、検索対策(SEO)を意識した文章が不可欠です。
たとえば、「苫小牧市 社労士」というキーワードで最初に1ページ目に入ると、地域の認知度が上がります。
この評価をしているのは、Googleの“ボット”です。
ホームページの中のコードや文章を読み込み、「このサイトは地域に役立つ情報を発信しているか」を判断しているのです。
こうやって収集したデータをもとに、検索順位は決められます。
デザイナーが一生懸命デザインされる画像や色という要素を、Googleのボットを評価していません。
見た目の印象は大事だけど、集客に力を入れたいなら、狙ったキーワードで上位表示できるSEO対策に長けたライターのほうが重要です。
つまり、ライターが書いた文章の質が、ホームページの集客力を大きく左右します。
ホームページは“作る”だけでなく、“見つけてもらう設計”も大切です
せっかく費用をかけてホームページを作るなら、「見た目がいいだけ」で終わらせず、「集客できる仕組み」まで意識したホームページにすることが大切です。
ホームページ制作会社の中には、デザインはしっかりやるけど、お客様(士業の先生)にホームページに載せる原稿提出を求めるところがあります。
これこそ、デザイン(かっこよさ)に全振りして、ネット集客(力)に注ぎこめていない例です。
デザイン重視のホームページは、高級旅館や美容クリニック・ネイルサロンなどにはいいと思いますが、士業の先生は集客につながるホームページを作ったほうが資産になります。
そのためにも、SEO対策(検索対策)のできるライターを入れるのは重要です。
予算が100万円あるなら、デザイン50%、文章50%に分けて予算を振るなどをして、長く使えるホームページを作ってみてください。
親和ホームページでは士業専門で見た目のデザイン以外にもこだわったホームページ制作をしています。
士業ホームページ制作でお悩みを感じたときは、ぜひお気軽にご相談ください。
親和ホームページでは、士業の先生向けにZoomでのオンライン無料相談を実施中です。
現在、無料のヒアリング相談で、30分間で、オンラインのZoom対応(平日夜・土日も可能)しています。
士業のホームページ制作は、実績のある親和ホームページがサポートするので、ご気軽にご相談ください。
▼ 無料のヒアリング相談のお申し込みはお問い合わせはこちらから。